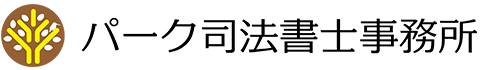今回は、親の宗教活動と、それに巻き込まれる子供について書いてみたいと思います。
特定の宗教を信じること、それ自体が信教の自由として憲法で認められていることは言うまでもありません。
しかし、親が良いと信じるものでも子供が望んでいない思想や活動を強制されているとしたら、それは許されるのでしょうか?
こんなことを考えるきっかけは中学時代にあります。
入学後すぐ、本読みの順番が回ってきたのですが、私は「施す」という漢字が読めず、もちろん意味もわかりませんでした。
すると、隣の席の子が、ボソッと「ほどこす」と読むのだと教えてくれました。
後から考えると、その子のうちは親御さんがある宗教の信者でした。
もしかしたら、そのために「施す」という単語を身近に見聞きしていたのかもしれません。
その子は、中学生になってからは自分の意思で活動には参加していないようでしたが、その話題に触れてはいけないという
暗黙の共通の認識が生徒の間にあったと思います。
先日読んだこちらの2冊。


またこの問題について考えるきっかけを与えてくれました。
『星の子』 今村夏子 著『カルトの村で生まれました』 高田かや 著
『星の子』は、両親が、病気がちな次女のため、知人が勧める特別な効能のある水を買い始めたことがきっかけで
宗教活動にのめり込み、仕事も辞め、家族の生活全体が宗教を中心に回り始めます。
そんな生活に反発を覚えた長女は、自立できる年齢でもあったので家を出て家族と距離を置きます。
しかし、著者である小学生の次女は、両親の宗教的な奇行(他人の目にはそう見える)を恥ずかしいと感じながらも、
両親の気持ちも理解できるとして、自分からは積極的に関わらないものの言われれば直に集会に参加します。
ある種の諦感とともに自分の置かれている状況を拒絶もせず、淡々と受け入れて折り合いをつけて生活しています・・・・・・
一方、『カルトの村で生まれました』は、特定の思想を持つ人々が自給自足の共同生活を営む村で、
幼少期から19歳までを過ごした筆者が、当時の生活の様子を綴ったものです。
その思想とは、共産主義的なもので、私有財産を否定し、全体の平等を目指しています。
この村では、子どもも農作業などの無報酬の労働に従事させられます。
また、親子は離れて暮らしたまにしか会えません。
著者は子どもながらに、この生活にどこか異質なものを感じつつ村から抜け出すこともなく時は過ぎていきます・・・・・・
小さな子供は自分が育った家庭環境しか知らないため、例えそれが世間一般から見たら変わった状況であったとしても、
あまり疑問も持たず受け入れてしまいがちです。
不満があっても抜け出す術を持ちませんし、親も良かれと思ってしていることなので虐待にはあたらないと思われます。
このような状況で、子供の親に言えない本当の気持ちを尊重したり、尊厳を守るにはどうしたら良いのでしょう?
私のなかで、長い間うっすら気になっており、時たま顔を出してきては考えさせられるも答えが出ない問題のひとつです。
そして、私自身も、今現在、無自覚に子供に何らかの思想を強制しているかもしれません。良かれと思って。
皆さんはどうお考えになりますか。